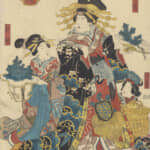江戸を熱狂させた平賀源内の「多才」
蔦重をめぐる人物とキーワード⑤
■晩年は自暴自棄の末にあえなく獄死
平賀源内は、1728(享保13)年に白石茂左衛門良房の三男として讃岐国(現在の香川県)で生まれた。早くから奇才の片鱗を見せており、1739(元文4)年には「おみき天神」というからくり仕掛けの掛軸を作成している。これは、紐で引っ張ると掛軸に描かれている天神の顔がまるで酒を飲んで酔っ払ったように赤くなる仕掛けで、近所の子どもたちがお神酒をお供えした後に紐を引っ張り、驚く様を観察していたという。
父が亡くなった1749(寛延2)年に家督を継承。その際に白石から平賀姓に改めた。白石家はもともと信濃国(現在の長野県)の武士で平賀姓を名乗っていたが、甲斐国(現在の山梨県)の武田氏に滅ぼされた後に奥州へ移り、伊達氏に仕えるようになってから白石になっていたらしい。
家督を継いだのと同時期に、源内は高松藩の薬園にかかわる役職に就いた。源内の才能を見抜いた高松藩藩主の松平頼恭(まつだいらよりたか)は、1752(宝暦2)年頃に1年の間、長崎への遊学を命じている。頼恭は藩内の殖産興業に熱心だった藩主で、高松城内に植物園を設けてさまざまな植物の栽培に取り組んでいた。藩の薬園で源内の仕事ぶりを見るにつけ、その才を見出したということなのだろう。
遊学中の源内はオランダ語や西洋医学、本草学を学んだ。本草学とは、薬用に用いられる動植物の形態や効能の研究のこと。江戸時代に大流行し、博物学的な学問へと発展している。
異国の文化や思想に触れたことで刺激を受けた源内は、1754(宝暦4)年に藩の職を辞退。妹の婿に家督を譲り、単身、江戸に向かった。なお、1759(宝暦9)年に源内は再び高松藩に登用されているが、わずか2年で辞職。この時に藩の怒りを買ったらしく、「任官お構い」つまり、他藩に仕えることができなくなった。
江戸では本草学者・田村藍水に師事。本格的に本草学や医学を学んだ。藍水は1757(宝暦7)年に日本初の薬品会を開催しているが、これは源内の発案だったという。やがて源内は本草学が薬学から物産学へと展開していくのに合わせ、自ら主催者となって物産会を開くようになり、国内の知識交流を主導。さらに医学の枠を飛び越え、火浣布(燃えない布)の発明をしたり、タルモメイトル(寒暖計)を製作したりするなど、日本の科学技術発展の礎を築いた。
一方で、戯作『根南志具佐(ねなしぐさ)』や浄瑠璃『神霊矢口渡(しんれいやぐちのわたし)』を刊行し、文学者としても注目を集めた。『西洋婦人図』という油彩画を描いて西洋画法を世に広く伝えたことも、彼の多彩な経歴のひとつとして知られている。
多才ぶりは金山や鉱山開発にも発展した。幕府をも巻き込む一大事業で、全国の鉱脈を訪ね歩いている。いずれも大きな手柄に至ることはなく、この頃から源内は、奇抜な天才といったような羨望の眼差しから、「山師」といった疑いの目を向けられるようになっていったらしい。
源内の名が再び輝きを放つきっかけになったのが西洋の機械である静電気の発生装置エレキテルだ。1776(安永5)年に、7年の月日をかけて復元に成功し、江戸に一大エレキテルブームを巻き起こした。日本で初めて電気を発生させた偉業だった。
ところが、「ガラスを以て天火を呼び病を治す」を文句に医療用具として宣伝し自身への出資を目論んだものの、理解する者がほとんど現れなかった。次第に源内は自暴自棄になっていったらしい。
1779(安永8)年11月には殺人罪で捕縛。大名屋敷の設計図を盗まれたと勘違いして、ともに飲酒していた大工を殺したものとされるが、理由は定かではない。同年12月8日に獄中で病死した。享年52。獄中で自傷を繰り返していたとの説もある。
数々の発明品や文学を残した源内の功績は、医師で蘭学者の杉田玄白(すぎたげんぱく)や洋風画家の小田野直武(おだのなおたけ)といった幅広い分野の才能を開花させ、影響を与えたという点でも大きい。
- 1
- 2